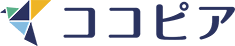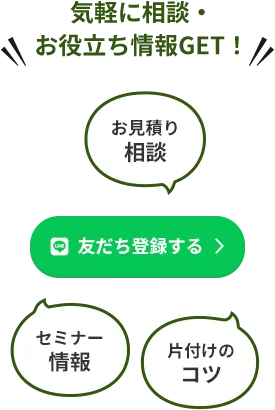こんにちは。
岡山・倉敷で遺品整理や生前整理を専門とするココピア、広報スタッフです。
前回の記事では、地震対策を意識した家づくりとして『床を片付ける』ことをお伝えしました。
今回は、自分の身長より高い位置にある『家具』について考えていきましょう。
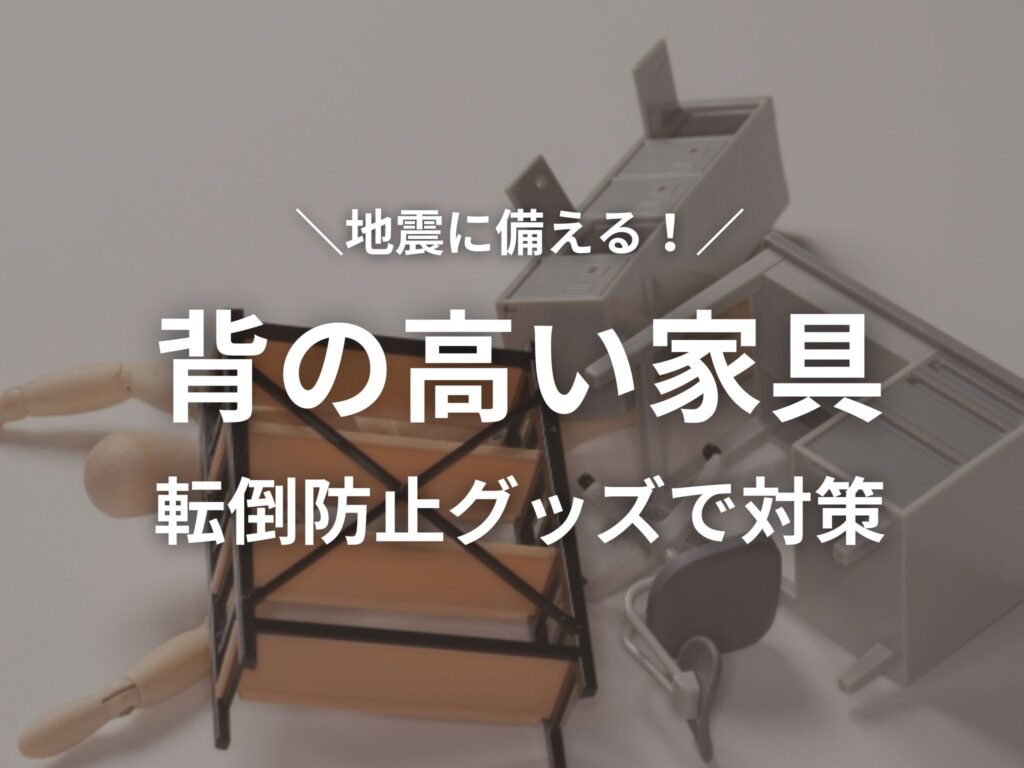
阪神淡路大震災は、30年前の1月17日5時46分という、冬の朝早い時間に起きました。
もっとも多かった死因は崩れた建物や家具による「圧死」だったそう。
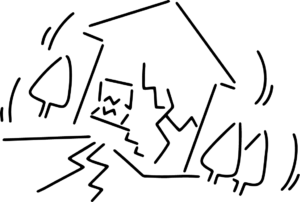
当時「関西で大地震は起きない」という漠然とした思い込みを持った方が多かったそうです。そうした意識の中、防災対策があまり出来ていなかったことも被害が拡大した原因の一つといえるでしょう。
ということで、今回は目線より上に危険はないか、考えていきましょう!
目次
床が片付いたら、今度は家具の安全を見直そう

床を片付けて避難経路を確保したら、次のステップとして高い家具の転倒防止対策に取り組みましょう。家具が倒れることで、以下のような危険が生じるため、家具の固定はとても重要です。
- 家具の下敷きになるリスク
- 家具の中身が飛び出してケガをするリスク
- 避難経路をふさぐリスク
特に、寝室やリビングのような長時間過ごす場所では、家具の転倒対策が命を守る鍵となります。
高い家具に対する具体的な地震対策
1. 家具を固定する

- L字金具や耐震器具を使う
→ 高い家具を壁にしっかり固定しましょう。賃貸住宅の場合、穴を開けずに使える粘着式の固定器具も便利です。
- 家具と壁のすき間をなくす
→ すき間があると家具が揺れやすくなるため、必ず壁に密着させましょう。固定器具を活用することで、倒れるリスクを大幅に減らせます。
2. 開き戸や引き出しの飛び出しを防ぐ

- 耐震ラッチを取り付ける
→ 地震の揺れで扉が開かないようにする耐震ラッチを取り付けましょう。特に食器棚、本棚、テレビボードなどには必須です。
- 中身を整理して軽量化
→ 中身が重いと家具全体の重心が高くなり、倒れやすくなります。不要なモノを整理して軽くすることで、安全性が向上します。
3. 家具の配置を工夫する

- 寝室には高い家具を置かない
→ 寝ている間に家具が倒れて下敷きになるリスクを減らすため、特にベッドの近くには高い家具を置かないようにしましょう。
- 重い物は下に、軽い物は上に
→ 重心が低い家具配置を作ることで、家具が揺れにくくなります。たとえば、本棚なら重い本は下の棚に、軽いモノは上の棚に収納しましょう。
4. 高い家具の上にモノを置かない

どうしても収納が必要な場合は工夫を
→ 高い家具の上に収納スペースを設ける場合は、落下防止のために滑り止めシートを敷いたり、収納ボックスを使って固定したりする工夫が必要です。ただし、できる限り置かないようにするのがベストです。
高い家具の上は「空っぽ」にする
→ 揺れによって、家具の上に置かれたモノが落下する危険があります。特に、花瓶や置物、本、家電などが落ちてくると、頭や体に当たって大けがをする可能性があります。
危険なモノを優先的に撤去する
→ ガラス製品や金属製のモノ、重いモノは特に落下時のリスクが高いので、優先的に撤去しましょう。
これを機に大型家具を手放すなら、ココピアにおまかせ!

昔は使ってたけど最近はあまり使ってないし、防災のためにも手放そうかな…と思う大型家具があれば、ココピアにご相談ください♪
専門スタッフが安心安全、即日対応させていただきます!
大きなタンス、ソファー、本棚などなど…ご自身では動かすことが困難な家具は、専門業者にお任せくださいね!
まとめ:高い家具対策で家族の命を守ろう

高い家具の対策は、一度行えば長期間効果が続き、家族の安全を守るための重要なステップです。
特に、「家具を固定する」「中身を軽くする」「高い家具の上にモノを置かない」という基本的な対策を組み合わせることで、地震時のリスクを大幅に減らすことができます!
防災対策は日々の小さな工夫の積み重ねが大切です。
まずは自分のことから、できるところから始めてみましょう!
そしてその後はご実家や親せきのお家など、大切な人のお家も見直していくと安心ですね✨